更新情報:記事内容、画像を変更(2025.2.20)
はじめに
このページは、愛知県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。
50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。
参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。
また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。
愛知県の由来についてはこちら
他の市町村についてはこちら
設楽町の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、「田口町」「段嶺村」「名倉村」と「振草村」の一部が、合併及び町制を施行したことによって、設楽町が成立しました。
町名に関しては、合併された地域が「北設楽郡」に属していることから、付けられたものと考えられそうです。
「設楽」という名称の由来については、いくつか説があるようでしたので、今回2つ紹介していこうと思います。
①設楽神と呼ばれている、人々が疫病を逃れる為に、信仰された神に由来してできた地名であるとする説。
②稲穂が垂れていた様子から、この「しだれる」が転じて「したら」となったとしている説。
- 読み方→「田口町(たぐちちょう)」「段嶺村(だみねむら)」「名倉村(なぐらむら)」「振草村(ふりくさむら)」
新城市の由来

1958年(昭和33年)11月1日に、元々あった新城町が市制を施行したことによって、新城市が成立しました。
「新城」の名称については、この地域にあった「新城城」に由来したものとなっているそうです。
昔、長篠の戦いで功績を挙げた、奥平信昌という人物が、徳川家康の長女を妻としてむかえた際に、新しく城を建てたとされています。
この新しい城こそが新城城であり、城の名称である「しんしろ」が、地名として定着しました。
ちなみに「しんしろ」という読み方になった理由ですが、建築される以前に「新城(しんじょう)」と呼ばれていた城があったことから、これと区別するためといわれています。
- 読み方→「新城城(しんしろじょう)」「奥平信昌(おくだいらのぶまさ)」
瀬戸市の由来

1929年(昭和4年)10月1日に、元々あった瀬戸町が市制を施行したことによって、瀬戸市が成立しました。
「瀬戸」という地名の由来については、複数の説がみられましたので、今回3つ紹介していこうと思います。
①陶器の産地として「陶所」と呼ばれ、これが「すえと」から「せと」へと転じたとする説。
②水陸の通路が狭いところを意味する、「狭戸(せと)」もしくは「狭門(せと)」から転じて「瀬戸」となった説。
③狭い山間を流れる川が急に開けた場所を「瀬戸」といい、瀬戸市もこの意味の言葉からきているとする説。
- 読み方→「陶所(すえどころ)」
高浜市の由来

1970年(昭和45年)12月1日に、元々あった高浜町が市制を施行したことによって、高浜市が成立しました。
「高浜」という地名については、衣浦湾にある崖に由来して、付けられたものといわれています。
というのも、衣浦湾と呼ばれる湾が愛知県にありますが、ここには大浜と呼ばれる場所があったそうです。
そして、この場所には高い崖があり、そのことから「高浜」と名付けられ、地名となりました。
ただし、この由来が濃厚であるといった情報はなかったので、あくまでそう考えられているといった感じになっています。
- 読み方→「衣浦湾(きぬうらわん)」
武豊町の由来

1891年(明治24年)2月17日に、元々あった武豊村が町制を施行したことによって、武豊町が成立しました。
「武豊」という地名は、武豊村ができた際に合併された村にある、神社の名前に由来したものとなっています。
ここで合併されたのは、長尾村と大足村という2つの村となっており、この合併によって武豊村ができました。
そして、長尾村には「武雄神社」が、大足村には「豊石神社」という神社がそれぞれあります。
この神社の名前から、1文字ずつ頭文字とってできた名称が「武豊」となり、由来となっているようです。
- 読み方→「武雄(たけお)」「豊石(とよいし)」
田原市の由来

2003年(平成15年)8月20日に、田原町が「赤羽根町」を編入、そして即日市制を施行したことによって、田原市が成立しました。
「田原」という地名については、当時この地に流入してきた人によって名付けられたとされています。
というのも流入してきたのは、熊野修験者と呼ばれる熊野三山の神社で修行をする人々であったそうです。
熊野三山は和歌山県にある3つの神社のある場所の総称で、この人々が当時の旧国名である紀伊国にある地名からとったとしていました。
現在の和歌山県にも、田原の名称は見られることからそういわれており、元々は集落の名称として、名付けられたものが広まっていったと考えられます。
- 読み方→「赤羽根町(あかばねちょう)」「紀伊国(きいのくに)」
知多市の由来

1970年(昭和45年)9月1日に、元々あった知多町が市制を施行したことによって、知多市が成立しました。
前身である知多町は合併により成立しましたが、これらの町は「知多郡」に属していたことと、知多半島に位置していたことに由来したものだそうです。
「知多」という名称の由来については諸説あるようでしたので、今回2つ紹介していこうと思います。
①当時この地域には田が多かったことから「千田」となり、これが転じて「知多」となったとする説。
②チガヤという植物が多く生えていたことから「茅田」となり、これが転じていったとする説。
知立市の由来

1970年(昭和45年)12月1日に、元々あった知立町が市制を施行したことによって、知立市が成立しました。
「知立」の表記が定まるまでは、「智立」や「池鯉鮒」といった表記もあったそうで、これが転じていったと考えられそうです。
「ちりゅう」という地名の由来については諸説あるようでしたので、今回2つ紹介していこうと思います。
①知立神社という神社がこの地にあり、この神社を建てた伊知理生命にちなんでいるとする説。
②茅という植物が生い茂っていたことから、「茅立(ちりゅう)」なり、これが転じたとする説。
- 読み方→「伊知理生命(いちりゅうのみこと)」「茅(かや)」
津島市の由来
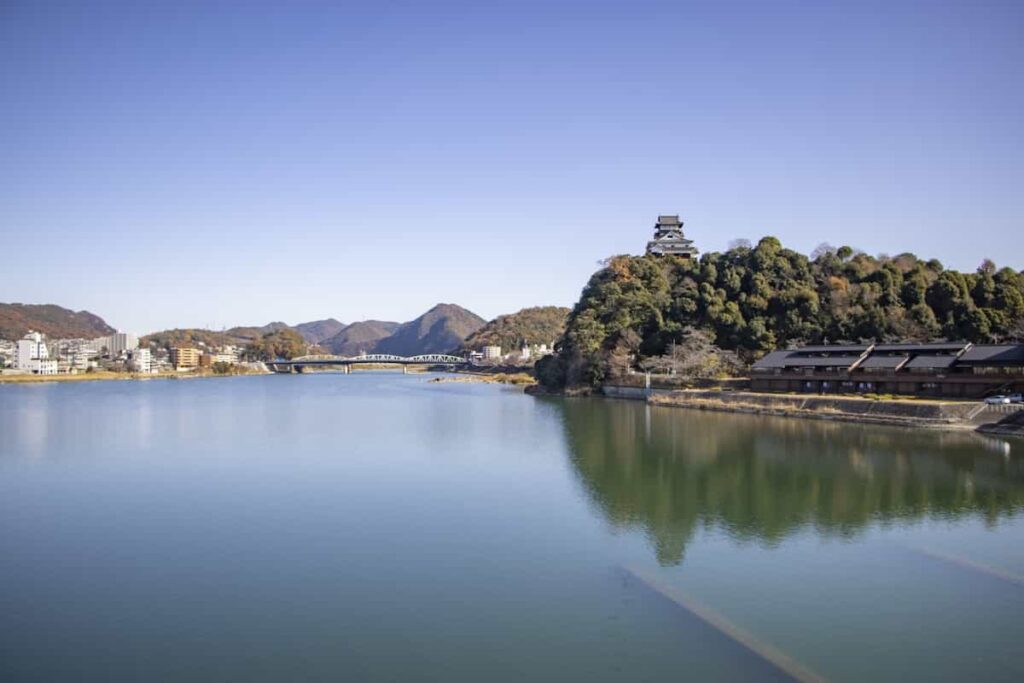
1947年(昭和22年)3月1日に、元々あった津島町が市制を施行したことによって、津島市が成立しました。
「津島」という名称の由来については、諸説あるとのことで、今回は3つの説を紹介していこうと思います。
①「津島」とは「船のつくところ」を意味しており、木曽川を下ると伊勢に行くことができたことからつけられた説。
②長崎県にある対馬は元々「津島」と表記されており、対馬に流されたスサノオがこの場所に辿り着いたことから、「津島」となったとする説。
③元々は海部郡に属していた場所であり、古くには「津積」と「志摩」という郷があったことから、これが合わせて「津島」となった説。
- 読み方→「対馬(つしま)」「海部郡(あまぐん)」
東栄町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「本郷町」「下川村」「御殿村」「園村」が合併したことによって東栄町が成立しました。
町名である「東栄」に関しては、由来についての情報を見つけることができす、不明となっています。
合併した村や町に、東栄の文字に関連しそうなところは見当たらなかったことから、合成地名でもなさそうです。
ただ、東栄町は愛知県の東部に位置している町であることから、「東」という字はこれに関連しているのではないでしょうか。
東栄町の由来については、また何か分かり次第、こちらに追加で記載をしていこうと思います。
- 読み方→「本郷町(ほんごうちょう)」「下川村(しもかわむら)」「御殿村(みどのむら)」「園村(そのむら)」
東海市の由来

1969年(昭和44年)4月1日に、「上野町」「横須賀町」が合併及び市制を施行したことによって、東海市が成立しました。
市の名称については公募が行われたそうで、何点かあった候補の中から「東海市」が選ばれています。
東海市は愛知県が東海地方に属していることに由来したもので、東海地方を代表するような名前として評価されました。
また、全国的にもよく知られている名称であることや、中心都市として相応しいといったことも、決定された要因となったようです。
ちなみに、東海地方の名称については、古い行政区分としての「東海道」に由来したものとなっています。
- 読み方→「上野町(うえのちょう)」「横須賀町(よこすかまち)」



コメント