更新情報:記事内容、画像を変更(2025.2.18)
はじめに
このページは、愛知県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。
50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。
参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。
また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。
愛知県の由来についてはこちら
他の市町村についてはこちら
岡崎市の由来

1916年(大正5年)7月1日に、元々あった岡崎町が市制を施行したことによって、岡崎市が成立しました。
名称については、元々は城地を指していたといわれており、いつしか地名へとなったとされます。
「岡崎」の由来については、主に2つの説があるとのことで、今回それを紹介していこうと思います。
①城や宿場が、「丘陵の出崎」にあったことからこれが由来とされ、こちらがよくみられる説。
②岡崎城を築上する際、土地が龍蛇のとぐろを巻いているように見えたことから、「いづれが尾か頭(さき)が知られず」からきたとする説。
尾張旭市の由来

1970年(昭和45年)12月1日、旭町が市制を施行及び改称をしたことにより、尾張旭市が成立しました。
そのまま「旭市」としなかったのは、既に千葉県に「旭市」があったことから、同名となることを避けたそうです。
市の名称についている「尾張」とは、現在の愛知県西部の辺りを指す、かつての行政区画名となっています。
「旭」の名称については、運気の上昇を表す「日の出」のイメージが由来となるといった情報がありました。
ちなみに「尾張」の由来に関しては、開墾された土地といった意味合いの「大治」が転じたとするなど、諸説あるようです。
春日井市の由来

1943年(昭和18年)6月1日に、「勝川町」「鳥居松村」「篠木村」「鷹来村」が、合併及び市制を施行したことによって、春日井市が成立しました。
市名については、合併された町村が「東春日井郡」に属していたことから、これに由来したものとなっています。
元々は、尾張藩の初代藩主である徳川義直によって、「春日井村」と命名されたのが始まりであるそうです。
「春日井」の名称に関しては、「春日大娘 皇女」という皇族が由来したものであるといった説がありました。
そこの領地を管理していた人々を、「春日氏」や「春日部」と呼んでいたそうで、それが転じて「春日井」の地名が生まれたとする説になります。
- 読み方→「勝川町(かちがわちょう)」「鳥居松村(とりいまつむら)」「篠木村(しのぎむら)」「鷹来村(たかきむら)」「春日大娘 皇女(かすがのおおいらつめのひめみこ)」
蟹江町の由来

1889年(明治22年)に、町村制が施行されたことによって、元々あった村の一部が合併して蟹江町が成立しました。
「蟹江」という名称については、町名にある通り蟹に由来して生まれた地名であるといわれています。
元々はこの地域は海に囲まれており、柳が繁って水辺にはたくさんの蟹が生息していたそうです。
そのことから自然に「蟹江」と、この地域の名称として、そう呼ばれるようになったとされていました。
歴史的にみると、1215年(建保3年)には「蟹江郷」の表記で登場しており、現在に至るまで残されています。
蒲郡市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「蒲郡町」「三谷町」「塩津村」が合併及び市制を施行したことによって、蒲郡市が成立しました。
「蒲郡」という名称は、1878年(明治11年)12月28日に合併が行われた際の、村の名称に由来しています。
そのときに合併されたのは、蒲形村と西之郡村で、この2つの村のそれぞれ1文字ずつとって、「蒲郡」となりました。
ちなみに、蒲郡村が成立した際の読み方は「かまごおり」であり、現在とは異なっていたそうです。
見つけた情報によると、蒲郡市が成立した際に現在の読み方となったそうですが、経緯については分かりませんでした。
- 読み方→「三谷町(みやちょう)」「塩津村(しおつむら)」
刈谷市の由来

1950年(昭和25年)4月1日に、元々あった刈谷町が市制を施行したことによって、刈谷市が成立しました。
「刈谷」という名称については詳しくは分かっていないそうですが、一般的には「狩谷出雲守」に由来するといわれています。
狩谷出雲守は、877年に出雲から一族を連れて、この地に移住してきた者の名であるそうです。
ちなみに古くには、「苅屋」などといった、現在とは違う漢字の表記があったことが分かっています。
どのような経緯で、現在の「刈谷」へと転じていったのかは不明ですが、刈谷城が築城されたこともあり、地名として定着していったようです。
北名古屋市の由来

2006年(平成18年)3月20日に、「師勝町」と「西春町」が、合併及び市制を施行したことによって、北名古屋市が成立しました。
「北名古屋」という名称についてはは、単純に名古屋市の北に位置していることに由来しています。
ちなみに市名については、公募が行われていたとのことで、絞られた候補の中から投票で決定されたそうです。
決定の理由として、海外からみても愛知より名古屋のほうが、知名度が高いといったことがありました。
その他、名古屋に関連づけて発展させていくことや、グローバルな見方をして、世界的にアピールできる名前であるといったことも、決定の理由となったそうです。
- 読み方→「師勝町(しかつちょう)」「西春町(にしはるちょう)」
清須市の由来

2005年(平成17年)7月7日に、「西枇杷島町」「清洲町」「新川町」が合併及び市制を施行したことによって、清須市が成立しました。
「清須」という名称は、洪水なども多く水と関係性の深い地域であるこもから、「水の出す清らかな洲」などの意味合いに由来しているのではないかと、一説にはあるようです。
14世紀には、「清須御厨」という名称がでてきたこともあり、歴史的にも古い地名であるといえます。
ちなみに「清須」だけではなく、「清洲」といった表記もあったようで、時代よってどちらが多かったかも違うそうです。
今回3町が合併したことにより新市が誕生しましたが、その内1つの町である「清洲町」と区別するため、「清須市」となったとされています。
- 読み方→「西枇杷島町(にしびわじまちょう)」「清洲町(きよすちょう)」「新川町(しんかわちょう)」「清須御厨(きよすみくりや)」
幸田町の由来

1952年(昭和27年)4月1日に、元々あった幸田村が町制を施行したことによって、幸田町が成立しました。
ちなみにこのときの幸田の読み方は「こうだ」であり、1954年(昭和29年)に豊坂村と合併したときに、現在の「こうた」となりましたが、経緯は不明です。
「幸田」の名称については、「広田村」にできた駅名に由来しており、この村名を改称したものとなっています。
というのも広田村に駅ができた際、既に広田駅はあったことから、駅名を幸田駅にしたそうです。
そして、村の名称と駅の名称が違うとややこしいなどの理由から、「幸田村」と改称することとなりました。
- 読み方→「広田村(こうだむら)」
江南市の由来

1954年(昭和29年)6月1日に、「古知野町」「布袋町」「宮田町」「草井村」が、合併及び市制を施行したことによって、江南市が成立しました。
「江南」の名称については、愛知県に流れる木曽川を「長江」にみたてたことに由来しています。
木曽川は、長野県から愛知県、岐阜県、三重県にまたがっており、中部地方においては一番長い川です。
そして長江とは、中国最大の川となっていて、世界でも3位に入る長さを誇る川となっています。
この地域はそんな木曽川の南側に位置していたことから、長江の「江」と南側の「南」をとって江南市となりました。
- 読み方→「古知野町(こちのちょう)」「布袋町(ほていちょう)」「宮田町(みやだちょう)」「草井村(くさいむら)」「木曽川(きそがわ)」
小牧市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「小牧町」「味岡村」「篠岡村」が、合併及び市制を施行したことによって、小牧市が成立しました。
「小牧」という名称の由来については、主に2つの説があるようですので、今回それを紹介していこうと思います。
①当時海があったことから船の出入りがあり、この場所にある山を目印に帆を巻いていたとされる。
そのことから「帆巻山」と呼ばれ、それが転じてたことによって、「こまき」になったとする説。
②馬を売買する場所であったことから、馬を「駒」という字で表現し、「駒来」と呼ばれていたのが転じたとする説。
- 読み方→「味岡村(あじおかむら)」「篠岡村(しのおかむら)」「帆巻山(ほまきやま)」
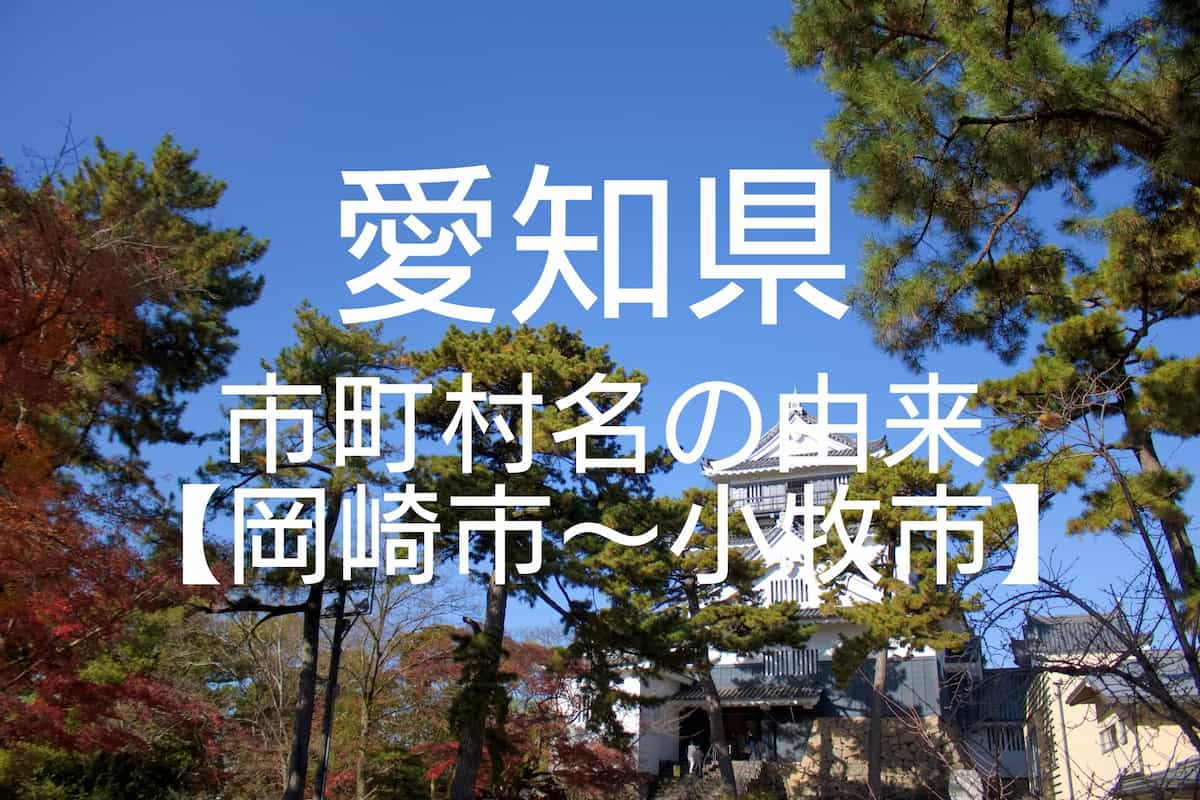
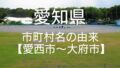

コメント