更新情報:記事内容を更新(2025.9.24)
はじめに
このページは、栃木県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。
50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。
参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。
また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。
栃木県の由来についてはこちら
他の市町村についてはこちら
那須町の由来
1954年(昭和29年)11月3日に、「芦野町」「伊王野村」「那須村」が合併したことによって成立しました。
町名の由来については情報が見つかりませんでしたが、この地域が「那須郡」に属していることにちなんだものと考えられそうです。
「那須」という地名の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。
①この地域にも流れる那珂川という川があり、「那珂川の中洲」を短縮したものとされている説。
②アイヌ語に由来するとされ、野を表す言葉が「ヌ」、裾を表す言葉が「シュ」と聞こえることから、合わせて「ヌシュ」となり、これが「ナス」になった説。
- 読み方→「那須町(なすまち)」「芦野町(あしのまち)」「伊王野村(いおうのむら)」「那須村(なすむら)」
日光市の由来
1954年(昭和29年)2月11日に、「日光町」と「小来川村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。
市名については、合併された町村の中にある日光町から名称を引き継いだ形となっています。
「日光」という名称の由来としては、この地域にある二荒山という山にちなんだものであるそうです。
空海という人物がかつてこの地に訪れた際に、「二荒山」のことを「にこう」と呼んだといわれています。
このことから「にこう」に対して「日光」の字を当て、地名として定着することとなりました。
- 読み方→「日光市(にっこうし)」「日光町(にっこうまち)」「小来川村(おころがわむら)」「空海(くうかい)」「二荒山(ふたらさん)」
野木町の由来
1963年(昭和38年)1月1日に、元々あった野木村が町制を施行したことによって、野木町かま成立しました。
前身である野木村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。
「野木」という地名は「奴宣」が転じたもので、古くには「奴宣郷」と呼ばれていたとされています。
しかし、どういった意味であるかなど、由来に関しての詳しい情報については見つけることができませんでした。
こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。
- 読み方→「野木町(のぎまち)」「奴宣(ぬぎ)」
芳賀町の由来
1954年(昭和29年)3月31日に、「祖母井町」「水橋村」「南高根沢村」が合併したことによって成立しました。
町の名称については、属している芳賀郡の中心として栄えたいという想いから命名されたといわれています。
古くには「芳宜」と表記されていたそうで、これが変化したことで「芳賀」になったようです。
この名称の由来については諸説あるそうですが、その中で見つけた説によると、川の氾濫により侵食された地形であったことに由来するとしています。
この地形を表す「ハガス」や「ハグ」といった言葉があり、これが転じたものであるそうです。
- 読み方→「芳賀町(はがまち)」「祖母井町(うばがいまち)」「水橋村(みずはしむら)」「南高根沢村(みなみたかねざわむら)」
益子町の由来
1894年(明治27年)3月1日に、元々あった益子村が町制を施行したことによって、益子町が成立しました。
前身である益子村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。
「益子」という地名の由来についてですが、調べてみても情報を見つけることができませんでした。
歴史的にみると、かつてこの地域は益子氏という豪族が治めていたことから、これに関係しているのかもしれません。
こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。
- 読み方→「益子町(ましこまち)」
壬生町の由来
1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことにより、2つの町村の区域をもって壬生町が成立しました。
ただし、元々壬生町という場所の区域があったことから、名称自体は以前よりあったようです。
そんな古くからある「壬生」という地名ですが、由来としては「乳部」が由来であるとしています。
この「乳部」とは、生まれたばかりの王子のお世話をする人々の職を指す言葉であるそうです。
これが現在の「壬生」へと表記が転じたことで、地名として定着していくこととなりました。
- 読み方→「壬生町(みぶまち)」「乳部(みぶ)」
真岡市の由来
1954年(昭和29年)3月31日に、「真岡町」「大内村」「中村」「山前村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。
市名については、合併前の町村の中で唯一の町である真岡町から名称引き継いだ形となり、地名の由来としては諸説ありましたので今回3つの説を紹介します。
①風が通る道などを意味する「マオカ」というアイヌ語を語源として、これが転じたものとする説。
②美しい丘があったことから、褒める際に使われる「真」の字を用いたことで「真岡」となった説。
③この地域に鶴が飛来し、舞っている姿が美しいことから「舞丘」と呼ばれ、これが転じたとされる説。
- 読み方→「真岡市(もおかし)」「大内村(おおうちむら)」「中村(なかむら)」「山前村(やまざきむら)」「舞丘(まいおか)」
茂木町の由来
1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって茂木町が成立することとなりました。
この町村制が施行される以前にも、茂木町自体はあったことから、古くよりある地名となっています。
「茂木」という地名の由来については、この地域を治めていた人物が「茂木氏」だったことに由来するそうです。
しかし、この人物名も元々あった地名からとったとする情報もあり、正確な由来は分かりませんでした。
こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。
- 読み方→「茂木町(もてぎまち)」
矢板市の由来
1958年(昭和33年)11月1日に、元々あった矢板町が市制を施行したことによって、矢板市が成立しました。
矢板町の前身となる矢板村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しているようです。
「矢板」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。
①肥えた田を意味する「八重田」や、田を焼く「焼田」からなど、田に由来するとされている説。
②この地域を支配していたのが「矢板氏」とされ、これに由来して地名となり定着したとする説。
- 読み方→「矢板市(やいたし)」「八重田(やえた)」「焼田(やきた)」


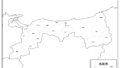
コメント