更新情報:記事内容を更新(2025.8.20)
はじめに
このページは、島根県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。
50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。
参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。
また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。
島根県の由来についてはこちら
他の市町村についてはこちら
海士町の由来
1969年(昭和44年)1月1日に、元々あった海士村が町制を施行したことによって、海士町が成立しました。
前身である海士村は、1904年(明治37年)に島根県における町村制が施行された際に成立していますが、名称自体は以前よりあったようです。
「海士」という地名の由来は、その名の通り「海士」という言葉をそのまま採用したものとなります。
海に潜って漁をするなどの人を海人といいますが、そのうち海士は男性を指す言葉であるようです。
ちなみに、一般的に女性の海人の場合は「海女」と表記するそうで、町名の表記とは異なっています。
- 読み方→「海士町(あまちょう)」「海人(あま)」
飯南町の由来
2005年(平成17年)1月1日に、「赤来町」と「頓原町」が合併したことによって成立しています。
町名については新たに命名されたものとはなりますが、どのようにして決まったのかなどは分かりませんでした。
また、「飯南」という名称に関しても特に情報をみつけることができず、不明となっています。
もしかすると、飯南町は「飯石郡」に属しており、「飯」の字もあることから「飯石郡の南」といったことからついたのかもしれません。
こちらの由来については、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。
- 読み方→「飯南町(いいなんちょう)」「赤来町(あかぎちょう)」「頓原町(とんばらちょう)」「飯石郡(いいしぐん)」
出雲市の由来
1941年(昭和16年)11月3日に、元々あった出雲町が市制を施行したことによって、出雲市が成立しました。
前身である出雲町は、同年の2月11日の合併により成立しており、このときに「出雲」と命名されたようです。
ただし、「出雲」の地名は古くからあり、その由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。
①「出雲」という漢字の表記が表しているとおり、雲がわき出る様子から命名されたと考えられている説。
②「五面」から転じたとされ、面というのは一つの地域を表し、五つの地域があったことに由来するという説。
- 読み方→「出雲市(いずもし)」「出雲町(いずもちょう)」「五面(いつおも)」
雲南市の由来
2004年(平成16年)11月1日に、「掛合町」「加茂町」「木次町」「大東町」「三刀屋町」「吉田村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。
市名については公募が行われたそうで、「雲南」というのは古くにこの地域に存在した「出雲国」の「南」に位置することに由来し、元々親しまれてきた名称だそうです。
元となる「出雲」という地名の由来としては出雲市の項目でも紹介していますが、ここでは他の2つの説を紹介していこうと思います。
①「イツモ」から転じたものとされ、「イツ」が神聖であることを、「モ」が藻を意味し、「厳藻」と表記されたのが由来とする説。
②同じく「イツモ」に由来するとしているが、ここでは「イツ」が神威を、「モ」は物を意味し、ここから「厳雲」となったのが転じたとする説。
- 読み方→「雲南市(うんなんし)」「掛合町(かけやまち)」「加茂町(かもまち)」「木次町(きすきちょう)」「大東町(だいとうちょう)」「三刀屋町(みとやちょう)」「吉田村(よしだむら)」「出雲国(いずものくに)」「厳藻(いつも)」「厳雲(いつも)」
大田市の由来
1954年(昭和29年)1月1日に、「大田町」「川合村」「久手町」「久利村」「静間村」「鳥井村」「波根東村」「長久村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。
市名はどのようにして決まったのかは分かりませんが、合併前にあった大田町から名称を引き継いでいます。
「大田」という地名の由来としては、かつて平安時代にみられた「邑陀郷」が転じたものであるそうです。
ちなみに「大田」の名称ですが、これは新たに開拓された広大な土地につけられることの多い地名といわれています。
実際、この地域も広い範囲に水田があったとされており、地名として定着したと考えられていました。
- 読み方→「大田市(おおだし)」「邑陀郷(おおだごう)」
邑南町の由来
2004年(平成16年)10月1日に、「石見町」「瑞穂町」「羽須美村」が合併したことによって成立しました。
新しい町名である「邑南」という名称は、合併された3つの町村の地域を表す言葉として親しまれてきたそうです。
この名称の由来についてですが、まず属している「邑智郡」の南にあることに由来したものとなります。
その他、「邑」は「ムラ」と読むこともでき、人が多く集まったところといった意味があるそうです。
そして「南」には人情や豊かさ、夢や希望といったイメージがあるということから、「邑南」が町名に選ばれました。
- 読み方→「邑南町(おおなんちょう)」「石見町(いわみちょう)」「瑞穂町(みずほちょう)」「羽須美村(はすみむら)」「邑智郡(おおちぐん)」
隠岐の島町の由来
2004年(平成16年)10月1日に、「西郷町」「五箇村」「都万村」「布施村」が合併したことによって成立しています。
新しい町名である「隠岐の島」については、どのような経緯、理由で命名されたのかは分かりませんでした。
推測とはなりますが、ここは隠岐諸島に位置しており、「隠岐島」とも呼ばれることに由来したものかもしれません。
「隠岐」という名称については、隠岐諸島を構成する島の1つ、「島後」が「沖の島」と呼ばれていたことに由来したものとしています。
これは他の島より沖合いにあることにちなんだ名称とされ、これがいつしか島全体を指す言葉になったそうです。
- 読み方→「隠岐の島町(おきのしまちょう)」「西郷町(さいごうちょう)」「五箇村(ごかむら)」「都万村(つまむら)」「布施村(ふせむら)」「島後(どうご)」
奥出雲町の由来
2005年(平成17年)3月31日に、「仁多町」と「横田町」が合併したことによって成立しています。
今回新たに町名がつけられていますが、どのようにして決まったのかについては分かりませんでした。
「奥出雲」の由来についても情報が見つかりませんでしたが、古くには「出雲国」と呼ばれる地域があったことから、これに由来したものと考えられます。
ちなみに、「出雲」という名称の由来としては諸説あり、実に様々な説が唱えられていました。
ある説によると、「エツモイ」といったアイヌ語に由来するとしていて、「エツ」が岬で「モイ」が湾港などを意味し、これが「イツモ」と転じたことで最終的に「出雲」となったとしています。
- 読み方→「奥出雲町(おくいずもちょう)」「仁多町(にたちょう)」「横田町(よこたちょう)」「出雲国(いずものくに)」
川本町の由来
1927年(昭和2年)4月1日に、元々あった川本村が町制を施行したことによって、川本町が成立しました。
前身である川本村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に2つの村の区域をもって成立していますが、以前より川本村は存在していたようです。
川本町には中国地方でも最大とされる「江の川」と呼ばれる川が流れていて、これが「川本」という地名の由来となっています。
「川」の字はこの江の川を、「本」とはほとりをそれぞれ意味しており、合わせて「川本」となりました。
この地域は、江の川を中心に発展してきた場所とも紹介されていましたので、地名の由来となるのも納得です。
- 読み方→「川本町(かわもとまち)」「川本村(かわもとむら)」「江の川(ごうのかわ)」

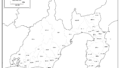

コメント